日本の音楽には、エネルギッシュでキャッチーな楽曲が多くありますが、その一方で、静かな時間に寄り添い、心を癒してくれる音楽も数多く存在します。こうした楽曲は、忙しい日常の合間に心を落ち着かせてくれる「Chill Music」として、新たな魅力を発信しています。
本記事では、「Chill Music Japan」をテーマに、静けさや癒しを感じさせる日本の音楽をいくつかご紹介します。選曲は私自身の好みに基づいているため、少し偏りがあるかもしれませんが、そんな主観的な楽しみ方こそが音楽の醍醐味だと思います。ぜひ皆さんも自由な視点で楽しんでみてください。
記事の最後には、今回紹介する曲をまとめたSpotifyプレイリストをご用意しました。お気に入りの時間にぜひ聴いてみてください。
細野晴臣:『薔薇と野獣 – New ver.』
「薔薇と野獣」は、彼の1stアルバム『HOSONO HOUSE』に収録され、1973年に発売されました。その後、2019年3月に発売された『HOCHONO HOUSE』では、「薔薇と野獣」が新たに録音され、現代の解釈で生まれ変わりました。このアルバムは、オリジナル版『HOSONO HOUSE』を新たに録音したものです。
細野晴臣の『HOCHONO HOUSE』制作過程に関するインタビュー記事も非常に興味深い内容です。驚いたのは、細野さんが制作中にモーニング娘。、エド・シーラン、テイラー・スウィフトといったアーティストの音楽に感化されたエピソード。こうした現代の音楽に触れている姿は意外でありながら、音楽の探求者としての姿勢が素晴らしいと感じました。
それにしても、歌声がほんとうに好きです。オリジナル版の頃と比較すると、声の出し方や響きには大きな違いがありますが、それも50年近くという歳月を経て培われた表現の深みなのだと感じます。一音ごとに時間の年輪が刻まれているようで、聴くたびに心に深く響きます。
泉まくら:『いのち feat. ラブリーサマーちゃん』
泉まくらのラップスタイルがとても好きです。力強い言葉で貫くようなラップももちろん魅力的ですが、この曲で彼女が見せる柔らかく丸みを帯びた日本語のラップには、新たな可能性を感じます。まるで日常のささやかな瞬間をすくい取るような繊細さがあり、誰かとのちょっとした会話や道端で目にする言葉――そんな日常のかけらが、静かに歌詞の中に溶け込んでいます。その結果、まったりとした落ち着きと、どこか心がほっとするような空気感が広がります。
一見すると、歌詞は日常の風景にインスパイアされたように思えますが、その根底には「生きる」という芯の強いテーマがしっかりと根付いています。この歌からは、自分の体で生き抜いてきた日々をすべて肯定し、これからの未来も力強く歩んでいくというメッセージが伝わってきます。
さらに、ラブリーサマーちゃんの声が加わることで、この曲の魅力は一層引き立ちます。彼女の柔らかで軽やかなボーカルが、泉まくらのラップに寄り添い、心地よい調和をもたらしています。
HOTEL DONUTS:『コンビニエンスボーイ 』/ TOSHIKI HAYASHI(%C) × maco marets × さとうもか × 山田大介
さとうもかの甘く柔らかな声のラップを中心に、男女のラップが繰り返される構成が印象的な一曲です。淡々と語りかけるようなそのスタイルがとても心地よく、この曲の大きな魅力になっています。
この曲は「インソムニアガール」という楽曲と対を成す関係にあり、どちらも同じEPに収録されています。どちらの曲も、決してハッピーとは言えない恋愛関係をテーマにしていますが、それでも「これでいいじゃないか」と自分に言い聞かせながら、安心と不安の間を行き来するような繊細な精神状態が描かれています。その姿は、聴き手に共感を呼び起こすと同時に、考えさせられるものがあります。2曲に言及したインタビュー記事はこちらから。
夏を描いた10のストーリー――さとうもかのクリエイティビティの根源に迫る! | スペシャル | Fanplus Music
「他者に対して言えなさ」がある一方で、「言いたいことを全部言えるようになったら、恋愛は消えてしまうのでは?」といった漠然とした疑問も浮かんできます。それでも、そんな内省的な問いを超えて、さとうもかをはじめとするパフォーマンス陣の心地よい声とメロディーが、聴く人の心を優しく包み込んでくれます。
坂本慎太郎:『ツバメの季節に』
2020年12月、コロナ禍真っ只中にリリースされたこの曲。当時、多くの人が抱いていたであろう「これからどんな未来が待っているのだろう?」という不安や期待が、この楽曲には表現されています。しかし、曲調は暗さを感じさせるものではなく、むしろ軽快で心地よいもの。私自身、この曲を定期的に聴いて癒されている一人です。
実を言うと、私がこの曲と出会ったのは、コロナ禍が過ぎ去った後でした。そのため、当時の状況を反映したというよりも、季節が移ろい、冬を越えてツバメが日本に渡ってくる春を待ちわびる気持ちとして受け止めました。こういった心境は、時代や状況を問わず、人々の心に普遍的に存在するものだと思います。
その意味で、この曲は特定の時代や状況に限定されず、もっと日常的で、季節の移ろいや心の中にあるささやかな期待感と、それに伴うほんのりとした不安感――そんな相反する感情が入り混じる瞬間を歌った作品のように感じられます。
羊文学:『白河夜船』
「白河夜船」(しらかわよふね)は、熟睡して何も気づかないさまや、知ったかぶりする様子を表すことわざです。この曲は、日本映画『白河夜船』をイメージして作られた作品です。映画は2015年に若木信吾監督が手掛けたもので、原作は1989年に発表された吉本ばななの小説です。
眠りをテーマとしたこの作品は、映画館の暗闇で観ていると、まるで主人公と一緒に眠ってしまいそうなほど静かな音響設計が特徴です。衣擦れの音や洗濯機の回る音、遠くで聞こえる電車の音などが響く中、音楽はほとんど使われていません。レースカーテン越しの淡い光、ベッドサイドの弱々しいライトの明かり、そして休日の夕方に目覚めたときの何とも言えない屈辱感――そういった感覚が、この曲の雰囲気に織り込まれているように感じます。
想い人に思いを馳せながら、ひたすら眠気に抗えず、それでもお腹は空く――若い頃の時間を持て余した休日のけだるさが、そのまま歌詞に表現されているようです。音数を抑えたアコースティックギターの響きが、このけだるさに絶妙に寄り添っていると感じました。この曲については、THE FIRST TIMESのインタビュー記事でも語られているので、ぜひチェックしてみてください。
君島大空&塩塚モエカ:『サーカスナイト』
羊文学つながりでもう一曲。『サーカスナイトは』もともとは七尾旅人が2012年にリリースした曲で、その後、君島大空(きみしま おおぞら)が羊文学の塩塚モエカをボーカルに迎えてカバーしました。この2人は、アーティストが一発撮りで楽曲を披露する日本の人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でも共演しているので仲がいいんでしょうね。君島大空が高校時代に羊文学のライブを観に行ったのをきっかけに10代のころから交流があるようです。
この曲は聴いていると、まるでサーカスのテントの中に引き込まれるような、不思議で特別な感覚が広がります。非日常の空間が音楽を通して目の前に広がり、この曲が持つ独特の感情を感じられるようです。
恋愛をサーカスの綱渡りに例えた歌詞は、夢と現実の狭間をさまよっているかのようで、さらに言えば、さまよい続けたいという願望すら感じさせます。その特別さは、何度聴いても心に残る力を持っています。
SEKAI NO OWARI:『陽炎』(かげろう)
この曲には2つのバージョンがあります。バンドのフロントマンであるFukaseがボーカルを担当したカバーバージョンと、オリジナル版で作詞作曲およびボーカルを手掛けた、バンドではピアノを担当するSaoriバージョンです。どちらのバージョンも甲乙つけがたい魅力を持っていますが、今回はオリジナル版を紹介します。
元々この曲は、2022年3月にリリースされたアルバム『scent of memory』に収録され、Saoriが歌っていました。その後、2022年6月22日に発売されたシングル『Habit』にFukaseによるカバーバージョンが収録されます。異なる表現方法で歌われた2つのバージョンが、それぞれの魅力を持っています。
Fukaseがこの曲について日本の音楽雑誌「ロッキング・オン・ジャパン」の取材で語った内容が印象に残っています。彼は「この曲が本当に好きで、いつか自分のボーカルでカバーしてみたい」と考えていたと話していました。そして、「自分はボーカリストとしての経験を重ねてきたから、申し訳ないがオリジナルを超えさせてもらうつもりでレコーディングに挑んだ」と語りつつも、「実際には、この曲が持つ特別な感覚を超えることの難しさを感じた」といったニュアンスの発言もしていました。その言葉には、オリジナルが持つ儚さや独特の魅力に対する深いリスペクトが込められていたように思います。
確かに、オリジナル版には独特の儚さや、感情を抑えながらも深く響く歌い回しがあり、聴く人を惹きつける不思議な魅力があります。さらに、彼女自身が作り出した言葉を自ら歌うことで、その表現には自然さと説得力が生まれているように感じます。
藤原ヒロシ ”Time Machine”
藤原ヒロシさんが何者なのか、知れば知るほどその肩書きがつかめなくなります。デザイナーかと思えば、音楽活動も行い、そのサウンドがまた圧倒的にかっこいい。肩書きや枠にとらわれない生き方を体現している、まさにその代表格ではないでしょうか。
彼がブルガリとコラボして商品を開発した際、「ファッションとはもっといびつでいい。着たいものを着ればいいだけ、ユニクロは最高のライフスタイルブランドだが、ファッションブランドではない」という趣旨のコメントを残しました。この言葉からは、彼自身の生き方や価値観、そして「何をかっこいいと感じているのか」が垣間見えます。
その感覚をもっと深く知りたいと思ったら、彼の楽曲「Time Machine」を聴いてみるのもおすすめです。藤原ヒロシという人物の一端を感じ取れる、そんな一曲ではないでしょうか。ちなみに、この記事を書いているまさにこの瞬間、私が身につけているものは、Kaepaのジャージ以外、すべてユニクロ製品でした。ユニクロ好きも藤原ヒロシを好きでいていいのです。
Chilli Beans. ”I like you”
この曲「I like you」は、2023年にリリースされたアルバム『Welcome to My Castle』の最後に収録されています。このアルバムは、そのタイトルが示す通り、バンドが作り上げた独自の世界観へリスナーを引き込むようなイメージで制作されたそうです。まるで「私たちはここにお城を立てました。どうぞ、このお城の中で思う存分楽しんでください」と言われているかのように。
アルバムの一曲目では、お城の重厚な扉が開き、そして閉じる音が印象的です。それはまるで「これからこの世界で存分に楽しんでください。途中退場は許しませんよ」といったメッセージを象徴しているかのよう。そんなコンセプトで作られたアルバムの最後を締めくくる曲として選ばれたのが、「I like you」でした。
この曲は、まるで夢の中にいるようなふんわりとしたサウンドが特徴で、歌詞は夢から目覚めるような内容です。バンドメンバーによれば、「この曲によって一度お城は消えるけれど、いつでも戻って来られる」という想いが込められているとのこと。アルバム全体を締めくくるにふさわしい一曲です。
個人的には、この曲をドラマ『時をかけるな、恋人たち』のエンディングで初めて知りました。吉岡里帆さんと永山瑛太さん主演のこのSFコメディーは個性的な内容で、最後にこの曲が流れることで物語が穏やかに締めくくられ、心が落ち着く感覚がありました。
藤原さくら ”いつか見た映画みたいに”
藤原さくらの柔らかなハミングで始まるこの曲。そのハミングが、この曲の持つチルな雰囲気を一層引き立てています。耳に触れる瞬間から、まるで心地よい空間に包まれるような感覚。どこか肩の力が抜けるような穏やかさを感じさせるこの曲は、聞くたびにリラックスした気分にさせてくれます。
この曲が収録されているアルバム『AIRPORT』は、トラックメーカーに依頼して楽曲を制作し、その上に歌詞を乗せるというスタイルで作られたそうです。トラックを手掛けたのは、主にヒップホップを手掛ける音楽プロデューサーのVaVa。スクラッチ音が印象的で、全体的にヒップホップ色の強い仕上がりになっています。それでもどこか緩く、まったりとした歌声が気持ちをほぐしてくれるような魅力があります。
歌詞は、「映画みたいにはいかないよね……人生って」というシンプルなテーマが中心です。人は感情に振り回され、スパッと別れたり前向きになったりするのが難しい――そんな、もやもやしたリアルな気持ちが描かれています。それでも、歌全体からは「まあ、それも人生だよね。しょうがないさ」という、どこか爽やかで清々しい気分が伝わってきます。
クボタカイ ”春に微熱”
クボタカイはラップバトルで堂々たる成績を収め、その才能を確かなものとしています。彼の歌詞は、耳心地の良い韻を巧みに踏みながら、それを誇示することなく、自然体で言葉遊びを楽しんでいるかのようです。そして、情景描写に重きを置いた彼の歌詞は、リスナーを曲の世界にスッと引き込んでくれる魅力があります。
例えば、この一曲では、温かな春の日差しの中で微熱のような恋心を抱く主人公が描かれています。小春日和のようなあなたの笑顔が、私を現実から少しだけ別の世界へと連れて行き、それはまるで別の惑星にいるような感覚。風邪を引いたように、いつもと違う不思議な感情を抱える様子が歌詞に込められています。
その描写はどこか非現実的で、恋愛映画のワンシーンを彷彿とさせますが、同時にどこかで確かに感じた記憶とリンクするようなリアリティも感じられます。春の訪れを心待ちにせずにはいられない、そんな一曲ですね。
Salyu × haruka nakamura ”星のクズ α”
「星のクズ」には、α(アルファ)とΩ(オメガ)の2つのバージョンがあります。αは、ギリシャ文字の最初の文字で「始まり」を象徴し、Salyuの歌声が紡ぐ感情の世界を表現したポップで親しみやすいアレンジが特徴です。一方、Ωは最後の文字で「終わり」を意味し、作詞作曲を手掛けたharuka nakamuraの音楽的世界観を全面に押し出した、より静謐で深みのある構成となっています。今回は、親しみやすさの中に深みを秘めたαバージョンをご紹介します。
この曲は、アニメ『TRIGUN STAMPEDE』のエンディングテーマとして使用されています。アニメで流れるショートバージョンも素晴らしいのですが、全体の良さを伝えるにはどうしても時間が足りないと感じます。この曲は、現代の楽曲としては珍しく5分以上という長さを持ちます。その全編を通して聴くことで深遠な世界観に引き込まれる一曲です。
ポジティブで明るい歌詞が逆に重く感じられることがある天邪鬼な私にとって、この曲の歌詞は特別です。心にほのかな光を灯すような優しい言葉で彩られていて、前向きな気持ちをそっと思い出させてくれます。そして、この歌詞の情緒を見事に歌声に載せることができるSalyuの表現力には、ただただ感服するばかりです。
いちやなぎ ”きっと”
この曲と出会ったのは、NHKラジオ番組『あとは寝るだけの時間』の中で、パーソナリティーの一人である又吉直樹さんが選曲して流したのがきっかけでした。彼の選曲によって、私のプレイリストはより多様なものになり、そのセンスには感謝しています。
そして、この曲の最大の魅力の一つが「声」。隣で語り掛けて寄り添うような親密さを感じる一方で、夢と現実の境界から響いてくるような、どこか非日常的な遠さを持つ――そんな特別な声質に心を掴まれました。インタビュー記事によれば、彼は音楽が生活に近づきすぎず、かといって遠すぎない「絶妙な距離感」を意識しているのだそうです。それは、音楽を一つの逃げ場やセキュアベース(安全基地)のように考えているからだといいます。
彼の考えには深く共感します。私たちは、時に現実の重圧やこの世界への不満を抱えることがあります。そんな中で「芸術やエンタメって何の意味があるんですか?」と問いかけたくなる瞬間があるかもしれません。でも、芸術やエンタメには、「あなたが見ている世界がすべてではない」とそっと教えてくれる力があるのではないでしょうか。彼の音楽を聴いていると、そのことを改めて感じさせられます。
長谷川白紙 ”シー・チェンジ”
この曲は、ピアノの旋律と歌声、そして息を吸い込むブレス音だけで構成された、とても美しい楽曲です。長谷川白紙といえば、超高速BPM、複雑極まるリズムと圧倒的な音数でリスナーを驚かせる楽曲のイメージが強いですが、こんな静謐で繊細な曲も作れるのだと思うと、その音楽的な幅広さには驚かされます。期待感がさらに膨らむことを禁じ得ません。
Spotifyで最も再生されている彼の曲は「毒」というタイトルの楽曲ですが、「シー・チェンジ」と「毒」を聴き比べてみると、同じアーティストとは到底思えないほどの違いがあります。その対比が、彼の音楽の持つ多面性をより際立たせています。家でまったりすることに飽きたら、毒を入れて外に繰り出すのもいいかもしれません。
Spotifyプレイリストで楽しむChill Music Japan
今回ご紹介した「Chill Music Japan」は、心を落ち着かせ、リラックスした時間を過ごせる楽曲を集めたものです。静かで温かみのある音楽は、日常の隙間にそっと寄り添い、気持ちを穏やかにしてくれます。どの曲もそれぞれの魅力があり、新たなお気に入りが見つかったのではないでしょうか。記事内で紹介した楽曲をまとめたSpotifyプレイリストもご用意しましたので、ぜひお好きな時間に聴いてみてください。音楽を通じて、心地よいひとときをお楽しみいただければ幸いです。
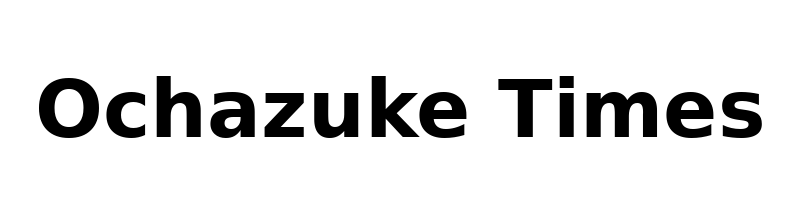



Comment